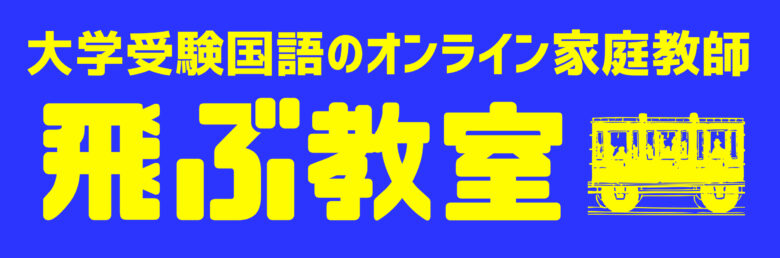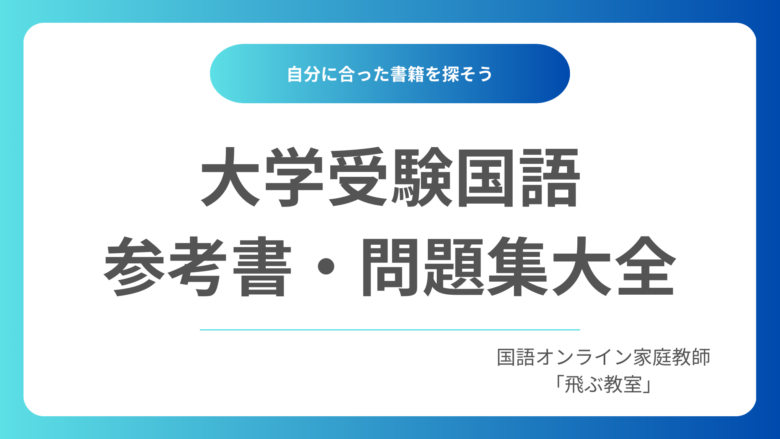孫泰蔵『冒険の書 – AI時代のアンラーニング』
2023年2月22日に初版が出版された孫泰蔵氏の著作『冒険の書 – AI時代のアンラーニング』を読んで私は大変膝を打った。膝は赤くなり、顔は青くなった。私はまさしくこの本をずっと求めていたように思う。
まず、この本は、起業家である著者自身が過剰な資本主義社会の中で覚えた「能力主義」への違和感や、いつまでも変わらない「学校制度」の問題を、思想史上重要な人物の考えを取り上げながら深掘りしていくことを主旨としている点がとてつもなく素晴らしいのだが、この素晴らしさを私と同じように味わうには、実はいくつかのハードルが存在する。そして、私はそのハードルをこれまで自力で必死で飛び越え、時には潜り抜けてきたという自負があるからこそ、この本に出逢った感動もひとしおだったのだ。
感動に必要なハードル①
まず第一のハードルとして、大人にせよ子供にせよ、この本の読者になるためには生きることに何らかのモヤモヤとした感じを持っていて、それが自分の受けてきた「学校教育」に起因するのではないか、と普段から疑いの目を向けている必要があるだろう。そもそもなぜ、つまらない話をじっと座って聞いていないといけないのか?学校を卒業して社会で働くようになっても、いつまでたっても同僚と業績の優劣を争い続けなければならないのはなぜか?
この社会に適性がある人間にとっては、そんなことに頭を悩ます価値も時間もない。つまり、いわゆる潜在的「社会不適合者」であることが第一のハードルであるのだが、たとえば発達障害診断が増加し続けている現代社会では、このハードルは年々低下しつつあるだろう。
感動に必要なハードル②
第二のハードルは、そうした日々の違和感の正体を突き止めずにはいられない知的な探究心や、精神的・時間的な余裕を持ち合わせているかどうかだ。多くの人はその違和感を胸に秘めながらも自制し、我慢し、なんとかうまくやっていくことができる。それは素晴らしいことであると同時に、今の社会のあり方を認めて、存続に協力する行為でもあるのだが。
私はそうして我慢することはできなかった。受験戦争を勝ち抜いて東京大学を卒業までしたにもかかわらず、いつも心のどこかに、「学校に通い続けてしまったことで失ってしまった何か」がある、心に空いた空洞があるような感じを抱えていた。そしてそれを埋め合わせるためにますます知識を求め、図書館や書店に通い詰めた。あらゆることは手探りで進めるしかなかった。そして4年ほど前のことだが、ついにある本と出会い、「青天の霹靂」を体感したのだった。
その本は、『冒険の書』にも登場する思想家イヴァン・イリイチの『脱学校の社会』だ。
この本でイリイチは、よく「学校は社会の縮図だ」と言われることがあるが、そうではなく「この社会は学校が作り出しているのだ」というコペルニクス的転回を行なった。学校の生み出した秩序が社会全体を覆い、学校の中の競争を勝ち抜いた人々が享受できる生活様式が「標準=理想」であるとする価値観。あるいは、「学ぶ」ことは「先生の知識(サービス)を受け取る」こととされ、多くのサービスを享受することが良いことだとされる価値観。
そうした中で次第に、生徒は自分で新しい知識を生み出す能力、本来の学ぶ能力を失ってしまうという逆転現象が生じてしまう。
あらゆる制度はそれがあまりに強固になると、その制度の本来的な目的とは真逆の効果を産んでしまうーー。この現象をイリイチは「逆生産性(counter-productivity)」として批判したのだった。
この根本的な批判に衝撃を受けた私は、この書物以外にも教育に関する書物を芋蔓式に手に取っていかざるを得なかった。フーコーやアリエスはもちろん、日本における学校制度の歴史など。
すなわちこれまでは学校に関する批判的考察を行うためには、最初の糸口を発見することにも、さらにそこから芋蔓式に本を読み解いていくことにも、なかなかの障壁があったのである。「社会学が社会批判をしても問題はないのに、教育学が教育を批判することは許されない」学問的状況、そして学校を神聖視する社会では当然のことだろう。実際、日本の教育学の入門的書籍を読んでみても、イリイチについては「さらっと」紹介される程度だったりする。
ところが『冒険の書』は、その糸口の発見と芋蔓式な知識の探索の二つの障壁をやすやすと取り払ってしまったのである。私の脳内やノートにだけ納まっていた思想の関係図が、そのまま非常に分かりやすい形で本の形になっている。
さらに当書は、今の形の学校ができてきた西洋での歴史的過程についてもくわしい点も魅力的だ(明治期以降の山縣有朋らを中心とした日本教育制度形成史に関しても書いていればより満足だが、瑣末なことかもしれない)。
一度出来上がってしまった制度や統治技術は惰性的に残りやすく、変革も非常に困難である。また、生まれた時からその中で暮らしている者にとっては、それが当然であり、そもそもその制度の必然性のなさに気づくこと自体が非常に難しくなる。まさに学校化社会はそうした空間だ。
「こうでなくても良かったのではないか?」と現状に対して問うてみること。歴史のIFを常に考え、違った可能性を考えることが重要だ。しかしそもそもその思考自体を奪うことこそが、学校の目的なのだ。「今の社会はこうなのだ。だから受け入れなさい。」
にも関わらずそれに抗い、学校制度の形成を捉える発想が、どのようにして孫泰蔵氏に芽生えたのだろうか。
こうした本を作るには著者や編集者の大変な労苦があったに違いなく、その労苦が身に染みてわかるのは、同じように苦悩した者の特権だろうと思い、嬉しい気持ちにもなった。
感動に必要なハードル③
第三のハードルは、ではそのような学校化社会をどう変革していくか、という問題意識を持ち、解決策を考え、実践に移しているかどうかという点である。私は(焼け石に水かもしれないが)自分のできる範囲で実践を行なっているため、『冒険の書』の内容には真に共鳴することができたのだ。
日本における学校化が最悪の形で露呈し、そしてそれを強化してしまっているのが、予備校をはじめとする受験産業なのだと数年前の私は考えた。
・世間的に良いとされる大学に入学することが良いことだという価値観を補強している点
・偏差値によってあらゆる大学と受験生を序列化し、能力主義を加速させる点
・より多くの、しかも高額なサービスを沢山受け取ることこそが、学びであると喧伝している点
・学習には「基礎」と「応用」があり、順に積み上げていかなければいけないと思い込ませ、そのためのサービスを大量に生産している点
など、枚挙にいとまなしだ。
そこで私は考えた。「あえて大学受験産業に関わることで、逆説的に、内部からそれを変革することはできないだろうか?」
その変革を可能にするチャンスがコロナ禍だった。コロナ禍によって、学校への登校は制限され、オンラインでの「授業」がひろく浸透したのだ。必要なときに、「場所を選ばず、一対一の関係で学びたいことを学ぶ」、50年も前にイリイチが構想した「ラーニング・ウェブ」の理想に、完全ではないにせよ接近できる時代がきた。
私は本を読んだりすることが好きで得意なので、ひとまず「現代文」を中心に扱おうと思った。そうしてできたのがこのオンライン個別指導「飛ぶ教室」である。その理念は以下の通りだ。
受験産業を脱学校化しよう

オンラインに慣れること
学校に通うことは、第一に「通勤の練習」という目的を持っている。賃金の発生しない「通勤時間」は、イリイチ的に言えば、賃労働を支えるタダ働き=シャドウワークの一部である(もっといえば学校は「労働者になる訓練をする期間」であり、勉強もまた賃労働者を育成するシャドウワークの一部である)。しかしこれからはそうしたシャドウワークはオンライン化で減少していくため、むしろ「子ども」はオンラインで仕事をする練習をした方がましだ。浮いた時間はもっと有意義なことやリラックス・睡眠につかう方がよい。
「学習は偶然に起こる」(イリイチ)
何かを勉強する時に一番頭を使うべきなのは、どうやって勉強するかを考えることであり、一番やりがいのある部分でもある。ところが、多くの受験生は予備校などにそれをお任せして、なるべく頭をつかいたがらないのだ。
たとえばカリキュラム主義を脱却し、問題集を使わず、志望校などの過去問をランダムに扱うこと。必要に応じて、その都度学ぶ課題を再設定すること。
これをすることで私自身が毎回学ぶ必要があり大変だが、毎回創造的な授業をすることができるようになった。実際にその方法で早稲田大学の合格者も出すことができた。
「基礎→応用」ではなく「応用→基礎」
過去問を扱い応用の仕方をさきに知ってから、足りない部分があれば自習によって訓練すればよい。
ギターを練習するときは何となく曲を演奏してみて、楽しさをしってから、コードを綺麗に弾く練習を重ねるといったような当然の順序が、なぜか勉強では突然通用しなくなる。
そんなことできないと思っている人も多いのだが、例えば実際に、指導している中学生に東大の問題を解いてもらったら、ある程度の補助があれば難なく問題に向き合うことができた。下手に勉強してしまっている高卒生よりもはるかに善く解けることには衝撃を覚えたが。
なおこの点について、『冒険の書』にも全く同じ主張が書かれていた。段階的な学習神話については是非問い直してみていただきたい。
『冒険の書』にも登場する、現在の教育システムの思想的ルーツであるコメニウスは、錬金術にも心酔し、錬金術的な発想で未熟な人間を段階的に「精練」しようと考えた。高校までの学習期間は12年間だが、12という数字に必然性があるか問うてみよう。それは錬金術において神秘的な数字だっただけで、実際の学習に要する期間とは無関係なのかもしれない。
「言語化力」を取り戻す
パノプティコン(一望監視式監獄)式集団授業は、教師が一方的に教えるばであり、「無口であること」が善であるとし、生徒を無口にさせる。無口を学習的に身につけた生徒は、対話を中心にした授業で、質問をしたりされたりする中で「言語化力」を取り戻さなければならないのだ。
無口になることを学習してしまっているのであれば、それを「アンラーニング」(学習を外すこと)することから始めなければならない。
「学び」に必要な好奇心を取り戻す
「素晴らしい文学作品でも、学校の教科書に載せられたとたんに「お勉強の題材」化し、つまらなくなる」という体験は誰しもあるだろう。冷静に考えてみれば、膨大な時間を費やして偉大な人間が考え、創り出した思想や文学が、そのような扱いを受けてしまうのは、不当であり、残念なことだ。これも学校化の悪弊である。
思想・文学に本当に関心のある人と学ぶことで、価値を見直す必要がある。
「脱常識」を徹底する
評論にせよ、小説にせよ、現代文の文章は「脱常識的」であるため、「常識を教え込む場」としての学校機関とは矛盾してしまう。その結果本質的なことは学校では教えることがそもそもできないのだ。
逆に言えば、脱常識的に考える思考法を身に付けるためにおあつらえ向きなのが現代文の読解であり、これからの社会においてはますます重要度を増す科目なのだと思う。
「専門化」を取り払う
学校化された社会は、「知識は偉い専門家だけが持っている」と思い込ませる社会でもある。「何も知らないお前は自分で知識を作り出せない」と。医師や弁護士ならまだしも大学受験レベルの学習内容ですら、英語、現代文、古文、漢文、日本史…と科目を切り分け、専門教師を割り当てる。
実際には、それぞれの分野は切り分けることができず、むしろ切り分けないで関連させた方がより深く理解できる。だから、現代文だけではなく、英語・古文漢文・歴史も必要な人にはサポートする。
「言語」の学校化を取り払う
学校は、「私は国語を勉強する」というような、「主語が対象を能動的に操作する」という形式の文法を学ばせる場でもある。「先生が生徒を教え込む」「生徒は先生に教えられる」といった能動・受動のみの関係が世界を覆っていると教える。これにより、近代社会は個人の責任や役割分担を明確にすることができたのだろう。
ところが実際には日本語は主語を重要視しない。古文を読めばそれはさらに明らかだ。真の「国語学力」のためには、学校文法では太刀打ちできない日本語の読解について考える必要があるだろう。
以上が私の考えた「脱学校化」戦略であり、他にも様々な方法がありうる。『冒険の書』を読んで、さらに多くの人がこの問題について考えて欲しい。
内容の価値に加えて、形式の妙も

実際には、生徒や保護者様方の「良い大学に合格したい /させたい」というご要望に応えなければ、仕事を続けていくことができないのが現状であり、バランスが必要になってくる。しかし、本当に「学ぶ」力が身につけば、大学受験くらいは簡単に乗り越えられるので、そこは何の問題もない。
話は随分と逸れてしまったが、要は私は「社会を脱学校化する」という課題よりも、「一人ひとりを脱学校化」するというより身近なところから始めようと思い、仕事をしている。そんな中で、その「脱学校化」に真摯に向き合っている『冒険の書』と出逢い、また、この書が評判を呼んでいるという事実に大変感銘を覚えたのであった。何より全く別の場所で、別の経験をしていた人が、同じ時期に自分と同じような思想の道を辿っていたということにも。
という訳で、当書の内容の素晴らしさについてはこれくらいにしておく。というか、内容はほとんど既に知っていたからだ。どちらかというと、私の感動の本質は、「既に知っているのに誰とも分かち合えなかった知識の網が、この本一冊にまとまっていること」だったのである。フーコーやイリイチはもちろん、親鸞やユクスキュルやデュシャンまでが連関して登場している大変稀有な書籍だ。もちろん、この本をきっかけにして、さらに他の書籍を読んでいく必要はあるが、そのきっかけを提供してくれているだけで十分価値がある。
内容よりも素晴らしいのは、当書の形式である。
・中高生でも手に取りやすい今風で綺麗な装丁
・内容の過激さとは裏腹に、タイトルにふさわしい冒険的ストーリー
・思想家たちがまるでそこにいて、話しかけてくるような臨場感
・難しいことを分かりやすく伝える平易な文体
・巻末のカラー地図
などなど、こんなにも刺激的な内容が堂々と一般書の風貌で店頭に並んでいるのだ。
また、出版のタイミングも素敵だった。
2023年、コロナ禍は終わったことになり、なぜか学校が大好きで学校なしには生きていくことができない人々が学校に戻り、今まで通り学校化社会を続けようとしている。そんな中全く別の観点から学校化社会に問いを投げかかけているのがopenAIのchatGPT(大規模言語モデル=LLM式の人工知能=AI)の登場だ。 当書の出後に登場したchatGPT-4は、学校の先生よりも親身で、自分の感覚を言葉にできない高校生よりは賢く、私よりも賢く、そのうち感受性豊かな中学生よりも情緒豊かになるかもしれない。学校化社会の中核を為すホワイトカラー職の代替もすでに起こりつつある。
コロナ禍の時代に、デヴィッド・グレーバーの「ブルシットジョブ」という概念が流行した。ホワイトカラー労働の多くが本人がその意味ややりがいを感じない仕事であるという指摘だった。
さらにopenAIが主張していることは受験生にとって非常に耳が痛い。「高度な知的作業を必要とする高給な職業から、AIによる代替が始まっていく」のだという。
学校の必要性がまた問われるべき瞬間が来ている。まさにそんなタイミングでこんな本が登場したということは評価してもしすぎることはないだろう(上から目線な言い方はよくない。「南無三」の方が適切かもしれない)。
「答えようとするな、むしろ問え。」と当書のカバー裏には書かれている。誰でもそれができれば私の仕事はいらなくなるかもしれない。まだまだ当分は必要だが、いらなくなった社会の方が善い。もっと楽しいことをやるだけだから。
※私自身は、「学校に行くな」と言いたい訳ではない。すでに学校が存在している以上、不登校という選択肢は、友達から疎外されたり、短期的にはすごく不利な結果になりうる。研究をしたいなら今の所は大学にも行くべきだ。大学受験一般入試には学校の成績は関係ないから、そっちは適当にやりすごしてしまえばいい。どうせやるなら、もっと善いやり方でやろう。