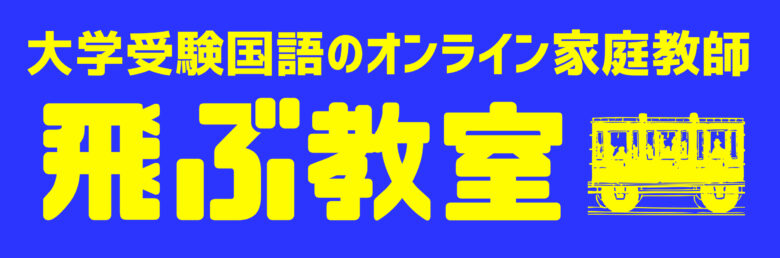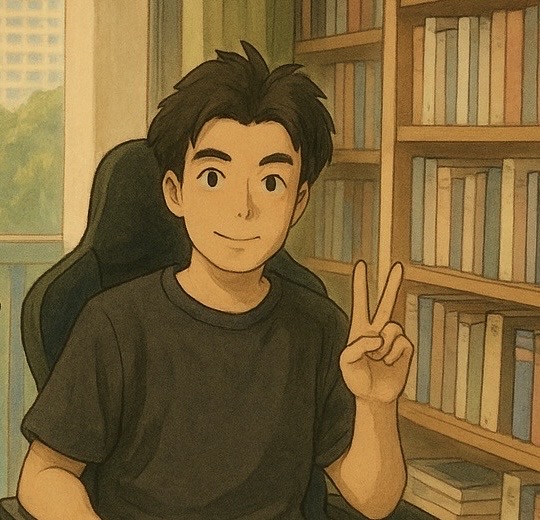大学受験の現代文の読み方は忘れよう
大学受験国語の指導をしていた受講生の一人が入試を終えたのち、その保護者の方から「大学(文学部)入学までの1ヶ月少しの間、『本の読み方とレポートの書き方』について指導して欲しい」とのご依頼を受け、指導を継続することになった。課題図書は『読んでいない本について堂々と語る方法』他数冊を予定。
たまにこういったご依頼があるが、こうした機会に私は、常々感じている「大学受験現代文の読み方の有害性について」、特に文学部に行く生徒には教えることにしている。受験勉強で蓄積された「毒」を抜くことが目的だ。大学受験で勝ち抜くための効率的な現代文の読み方は、残念ながら人生や学びにとってかなり有害だと私は考えているのである。その読み方を自ら教えているにもかかわらず。
今日はその「有害性」をいくつか列挙しておこうと思う。当然だが、あくまで主観的な内容である。
大学受験現代文の読解法の問題点
問題点① 速読
私はアンチ速読である。正確にはアンチ意識的速読と言うべきか。たくさん読書を重ねてきて、知識や経験が蓄積され、結果的に速く読むことができるようになることは問題がない。問題は大して読書経験のない大多数の高校生が、入試の時間制限に翻弄されて、無理に速読をしなければいけない状況である。無理に速読をして、内容を正確に理解したり、人生に役立つ知識として長く留めておく記憶に昇華させたりできるわけがない。10分後に内容を聞いても説明できない受験生がほとんどだ。
一冊の本を自分のものにするためには、じっくりと時間をかけて、舐めるように読むしかないが、それを勧めてくれる学校の先生はいないのだろうか。給食の時間にはゆっくり噛んで食事をすることが推奨されることと対照的である。
問題点② 再読しない
速読と同様に、入試の時間制限という事情から生じる問題点が、再読しないことである。厳しい時間内に再読なんかしていると問題を解ききれない。一度だけ読んで問題を解くのが理想的解法だろう。
しかし、それで文章の内容を本当に掴み取るができるのだろうか。特に小説などで顕著だが、最後まで一旦読み切ってから、改めて読み返すことで全体の中でのその細部の位置付けが理解できるというのが、一瞬で全体像を把握できる絵画と違って、直線的にしか鑑賞できない文章の本質である。
ロシア出身の文学者ナボコフが言う通り、「ひとは書物を読むことはできない、ただ再読することができるだけだ。良き読者、一流の読者、積極的で創造的な読者は再読者なのである。」(「良き読者と良き作家」『ナボコフの文学講義』上)
問題点③ 自分で読む本を選ばない
どこの馬の骨か分からない作問者が選んだどこの馬の骨か分からない著者の本をなぜか読まされるのが受験現代文である。しかし、その文章内容はあたかも真実であり価値があることを述べているかのように偽装されて受験生の前に現前する。その文章は論理的に矛盾がなく、綺麗な正しい日本語であり、構成も適切であると思いこませられる。
入試問題であるということそのものが帯びる権威性がそうしているのだ。「この文章は正しく美しく読む価値がある。理解できないお前が間抜けなのだ。」
しかしたくさんの入試問題を読めば分かることだが、どうでもいいことについて述べていて論理的矛盾を抱えている悪文が山ほどある。そういう文章ほど受験生を混乱に陥れやすく、篩にかけやすいからだ。
人生は短く、再読には時間がかかる。再読するほど価値のある本を探し出すために、情報を仕入れ、積極的に読む本を選択することが本来重要なことである。
問題点④ 筆者が誰か調べない
ある発言や文章が信頼にたるものかどうかは、その発言者や筆者の信憑性と切り離せないが、ほとんどの受験生はそれについては一切調べない。成績と無関係だからだ。その本の置かれた時代背景などの文脈についても同様である。
あらゆる文脈から切り離された数ページの文章を読み、読みっぱなしにする。この経験は受験に特有であり、その後の人生では起こり得ない「かけがえのない」経験だが、考えてみればとても気持ち悪く、無意味なものだろう。
問題点⑤ 辞書を引かない
辞書を引かないで文章を読んでいいのは受験の時だけである。自分勝手な言葉の定義で偉そうに話していいのはハンプティダンプティだけである。知らない言葉は辞書を引こう。
問題点⑥ 他の本との関係を調べない
これは問題点③④と関係している。「教養」を身につけたり、時間をかけて読むべき本を選別したりするためには、一冊の本が結ぶ他の数百冊の本との関係性を知ることが重要である。
問題点⑦ 感想を持たない
あくせく文章を読み、問題を解いている内に、受験生が本来持っていたはずの瑞々しい感受性がどんどん死滅していく。難関大を目指す、一見「よく読める」受験生にも顕著な傾向である。
「この部分はどういう意味か」は答えられても、「ここを読んであなたがどういう感想を持ったか」については答えられず、当惑の表情を浮かべるだけ。
感想を持たない読書に意味などない。自分と結びつけて読むことが本来の人間の読書ではないかと思う。
問題点⑧ 批判的に読まない
これは問題点⑦と似ていて、問題点③に起因している。
現代文の入試問題は大抵、「どういうことか」とか「なぜか」といった理解を問う問題であり、「筆者の意見を批判せよ」という問題は少ない(慶應文学部などの小論文は除く)。
しかし、受験で読まされる文章に限らず、人生でこれから読んでいく文章には欠点がたくさんある。盲信せず、自分の意見を持ってツッコミを入れていこう。
特に大学で研究者になりたい人は、この点は重要である。先行研究を批判的に読んでいくことが研究の第一歩だからだ。
問題点⑨ 自分で問いを立てない
現代文の入試問題では、文章のある箇所に作問者があらかじめ傍線部を引いてくれていて、その箇所について何らかの小難しい問題を用意してくれている。これは当たり前のことだが、考えてみればとても親切なことだ。
大学での研究では、その問い自体を自分で作って、自分で答えを探していかなければいけない。誰もお膳立てしてくれないこともある。人生も同じだろう。
問題点⑩ 文章が短い
長い長いと言われる入試問題でも、せいぜい数ページである。これに慣れてしまうと、たかが200ページの新書ですら読み通せないような読書体力のない人になってしまう。数十ページ前に書かれていたことをすっかり忘れてしまう。しかも読む価値のある本は大抵もっと長いものだ。受験を終えたら、リハビリとして少しは長い本を読んでください。
呆れる
ざっと書いただけで10個も問題点があった。
「誰かが勝手に選んだ本のごく僅かな数ページを、やみくもに急いで無批判に読み、読みっぱなしにし、辞書も引かず、筆者や関連する本について調べず、これといった(「難しい」以外の)感想も抱かず、聞かれたことにだけ答えられる程度に理解する」読み方こそが、受験現代文において王道の読み方なのである。そのこと自体というより、やむにやまれぬ事情でそういう読み方を受験生に許容せざるを得ない自分に呆れてしまう。
こういう読み方をしていては学べるものも学べないし、人生が色褪せるので、受験が終わったらさっさと忘れてしまった方がいいです。