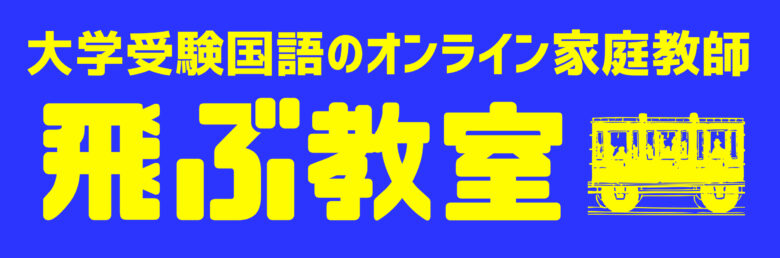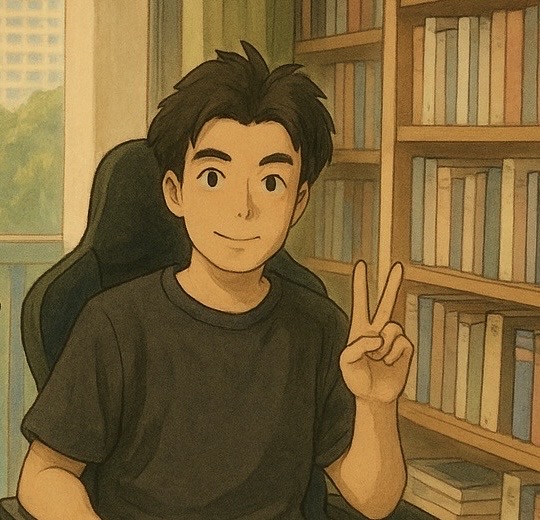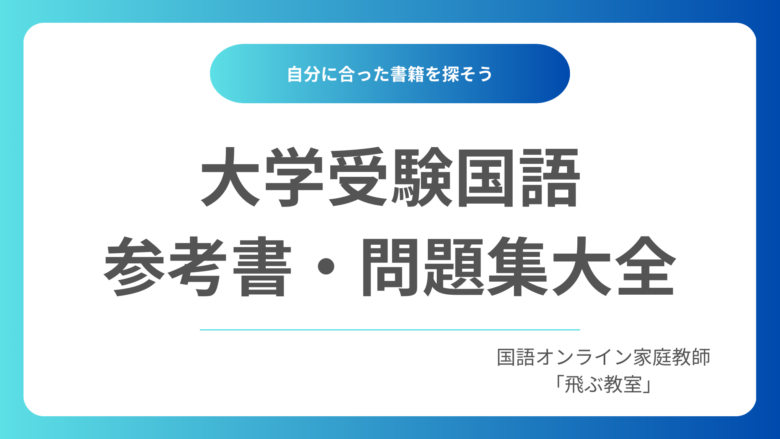オンライン家庭教師「飛ぶ教室」講師のけんです。
秋に入ってきて、多くの受験生が焦り始めるのが、「文学史」をどうやって勉強するのか?ということです。実際、学校の授業でもなかなか体系的に勉強できず、良い参考書がどれかもよくわかりませんよね。
そこで今回は、おすすめの参考書と、早稲田大学などの難関私大文学部でも解けるようになる勉強法をご紹介します!
文学史・おすすめ参考書
『原色シグマ新国語便覧』(文英堂)…おすすめ度:★★★☆☆
まずは言わずと知れた、「国語便覧」です。他社出版のものかも知れませんが、学校で配られたりして持っている方も多いと思います。え?参考書じゃないだろ?その通りです。。
なぜ一冊目が国語便覧かというと、これに載っている内容をしっかりと覚えれば、基本的に大学受験に必要な文学史、さらには古文常識まで網羅することができるからです!逆に、載っていない内容は覚えなくても大丈夫、という指標にもなります。
ただし、重大なデメリットが2つあります。
1つは、あまりにも網羅的で、内容が豊富すぎるため、どの知識が大事なのかが初学者にはわかりにくい、ということ。
当教室では、入塾直後から過去問を一緒に解いていき、実際に文学史問題に触れてもらって、何が聞かれるのか、どこが大事なのかを優先順位をつけて教えていくので、便覧だけで入試に挑む生徒もいます。
しかし、完全独学の場合はこの本だけでは正直難しいです(ただしその場合も、この記事の後半で勉強法を解説しているので、是非ご覧になってみてください。)。
2つ目は、単純にデザインが見づらい点です!参考書は手にとったときにモチベーションが上がることが一番大事です(私見)。3段組み、4段組みは当たり前で、字も小さいので、私は正直便覧で勉強する気にはなりませんでした。
というわけで、便覧を使わないで文学史を学ぶ最適な書籍を紹介していきます。
『原色新日本文学史』(文英堂)…おすすめ度★★★★☆
便覧と同じく文英堂から出版されている『原色新日本文学史』です。こちらが理解本としては最強だと思います。上代から近代までの日本文学史を順にまとめていて、各章が各時代の特色の概説や見やすい年表に始まり、ジャンルや人物についての詳細な注釈が載っています。それでいてレイアウトが非常に美しく、面白く読める一冊になっています(絶賛)!
最大のメリットは、年表のまとめ方が秀逸な点です。中古代平安時代ならその時代の文学が、年号とともに見開きで一望できます。これだけで十分買いです。
便覧と比べると、文法や古文常識、漢文についてはバッサリカットされていますが、他の参考書で勉強すればなんの問題もないと思います。早稲田大学などの難関入試でも、主に日本文学史についてのみ聞かれる出題傾向のところが多いですので、やはりこの本が最適かな、と思います。
まずはこの本を通読してから、細かい知識が必要になってから注釈の部分を読んでいけば良いでしょう。
星4つにしたのは、残念ながら問題演習がないからですね。ですので、次の問題集もセットで取り組むと万全です!
『頻出・日本文学史』(河合出版)…おすすめ度★★★☆☆
文学史に絞った問題集としては、数少ない選択肢の一つがこの『頻出・日本文学史』だと思います。
物語などのジャンルごとに系統図が書かれていて概説が載っている前半部と、実際に大学入試で出題された、実践的な問題を集めた後半部に分かれています。漢文の文学史も載っている点がGJ。
先に紹介した本である程度の知識をつけたら、この本の問題をどんどん解いていって、わからないところは理解本に戻って読む、という作業を繰り返すと、スピーディに文学史を攻略できると思います。
デメリットとしては、年表がジャンルごとになっていて見づらい点です。実際の過去問では、ジャンル関係なく年代順に並べることが要求されることも普通にあるので、年代の整理にはジャンルごとは不向きと言えます。『新日本文学史』の年表は、ジャンルに関わらず年号とセットで並べられていて、全体像を知るのにはこちらを用いた方が絶対にいいですね。
巻末には、文学史ベストという章があり、大学入試出題された回数が多い作家のランキングが掲載されていますが、これは特に気にする必要はないかと思います。あなたが受ける学部の過去問をしっかり分析するのをおすすめします。
注意事項としては、難関入試では、文学史の知識を本文と関連させて理解することが求められますが、この本ではその演習をすることはできないということです。当オンライン家庭教師「飛ぶ教室」では、逆に、文学史の知識を本文の読解に役立てる方法まで指導しております。
番外編①:おすすめしない参考書『SPEED攻略10日間 国語 文学史』(Z会)
題名からお察しの通り、直前期になって「藁をもすがる」思いの人がターゲットの参考書です。表面的な理解でもいいから、点数を取りたい!と思っている理系受験生がよく手に取ります。
ただ、時代ごとに概説と実践問題がコンパクトにまとまっているので、河合出版の問題集の代わりにこちらを使用するのもアリかもしれません。一問一答で地歴の知識を叩き込むのが得意な方はこちらでもいいですね。おそらく思考力は身につかないですが。。
番外編②:おすすめしない参考書?『日本文学史序説』(上下巻・ちくま学芸文庫)
こちらは日本文学の学生にはおそらく言わずと知れた、日本知識人の代表格・加藤周一による日本文学の概論的書物です。東大医学博士でありながら世界的な批評家ということで、昔の知識人の幅の広さには驚嘆しますね。。。
もちろん受験生には猫に小判の一冊ですが、常日頃日本文学に親しみ、受験なんて楽勝!という方、文学部で日本文学を専攻したい暇人にはマストアイテムでしょう。単に日本史を勉強するよりも、日本人の精神史を学ぶに役立つかもしれません。
文学史はどうやって勉強するの?
以下の記事で古文自体の勉強法も徹底解説していますが、文学史についても優先的に学んでほしい内容があります。
読解の勉強と同時並行にやろう!
……早うの人は、我より高き所にまうでては、「こなたへ」となきかぎりは、上にものぼらで、下に立てることになむありけるを、……
早稲田大学文学部2017年度入試、『大鏡』より
過去問読解の指導をしていると、この文章の「早うの人」ってどういう意味?と尋ねられました。もちろん、「早起きする人」という意味ではありません、と答えました。
出典を見てみると、『大鏡』とありますね。『大鏡』は平安時代後期の、紀伝体の歴史書。と文学史では覚えます。850年頃から1025年頃までの歴史を、その何十年か後から振り返って著した書物です。
つまり、『大鏡』の書き手にとって、物語の登場人物たちは過去の人物で、当時の習慣は書き手の時代とはすっかり変わってしまっていて、そのために昔あった習慣を補足しておいたのが、引用の文なんですね。
だから「早うの人」とは、書き手より早い時代の、登場人物を含めたその時代の人々のことだということです。
この例からおわかりのように、古文読解では文学史の知識がないと理解できないということがよく起きます。なので、文学史の知識は読解の勉強と同時に行っていくのがいいと思います。
で、何から勉強すればいいの?

STEP1:重要作品の年号と、成立順を覚えよう
文学史といっても幅広いので、何から手を付けるか迷いますよね。
古文の出題で圧倒的に多いのは、中古代と呼ばれる、平安時代の文章です。文法的にも、この時代のものを模範として学校で教わり、そこから中世以降の変化を覚えていくのが王道です。
なのでまずは、平安時代の文学史の年表を覚えていきましょう。
…といっても、それでも初心者には情報量が多すぎます。そこでおすすめしたい方法は、圧倒的に重要な作品の成立年をしっかりと覚えることです。
・凌雲集(814)
・古今和歌集(905)
・源氏物語(1008)
・大鏡(1108以前)
平安時代はだいたい百年おきに、上記の作品が登場しています。まずはこうした年号をしっかりと覚えてしまいましょう。
それから他の作品にであったときに、その作品が上の4つと比べてどれくらいかを覚えると良いです。例えば……
・蜻蛉日記はいつ成立?
年表を見れば、974年頃と書かれていると思います。具体的な年号は覚えなくても大丈夫です。入試では「年代順」に並べる問題がほとんどです。つまり、
「蜻蛉日記は古今集よりあとで、源氏物語よりも前」というように、相対的に成立年代を把握することが最重要課題です。
そこからだんだんと、覚えられる年号を増やしていき、解像度を上げて記憶していきましょう。
STEP2:作品の内容・評価を覚えよう
例えばこういう問題が出ます。(早稲田過去問から一部改変)
問:登場人物である、俊成の子「左少将」は『新古今和歌集』の選者でもあった。彼の著作を以下から選べ。
1:今鏡 2:近代秀歌 3:とりかへばや 4:山家集
では、作品の内容からアプローチしてみましょう。
『今鏡』は『大鏡』同様歴史物語。『とりかえばや』は男女の子供が性別を入れ替えられて育てられるお話。山家集は、西行法師が山で詠んだ歌集。消去法で、2『近代秀歌』が正解ですね。
難しい?今はわからなくても大丈夫です。ともかく、作品のジャンルや簡単な内容をおさえておけば、『新古今和歌集』の選者だったら、変な設定の物語は書かないだろうし、山ごもりもしないシティボーイに違いないし、歴史書を長々とかかないだろう、という想像がつくようになります。
という訳で、年代順を覚えた後は、それぞれの内容やジャンルを大まかでもよいので覚えていきましょう。作者と作品タイトルを一問一答で丸暗記するよりも、よっぽど役に立ちますよ。
STEP3:「〇〇〇」の文学

ところで、『源氏物語』といえば、「あはれ」(情緒)の文学と習いますよね。『枕草子』なら「をかし」(知的感動)の文学。
では、『新古今和歌集』は何の文学?と聞くと、答えられる人はぐっと減ります。
答えは「幽玄」の文学。鎌倉時代以降、重視されていくようになった美的感覚なんですね。
同時代の教養人には、しばしば共通の美的感覚があります。それが時代を経るごとに、どう移っていくのかを意識して勉強すると、全体的な文学史のイメージが掴みやすくなります。
そうすることで、読解のときにも、「大体こういう感情を詠んだ歌だろう」と目星をつけやすくなったりもします。是非覚えてみてください。
まとめ
という訳で、文学史のおすすめ参考書と、勉強法について解説してみました。
これを参考にして、是非とも志望校合格を目指してください!
学校や学部によって出題傾向はかなり変わってきますし、文学史と読解をどう結びつけるかは書ききれなかった部分もあるので、気になったかたは是非、オンライン家庭教師「飛ぶ教室」で、全国どこでも私の授業が受けられます。無料体験・相談をお待ちしております。
「飛ぶ教室」について以下から詳しく知っていただけます。
ではでは。