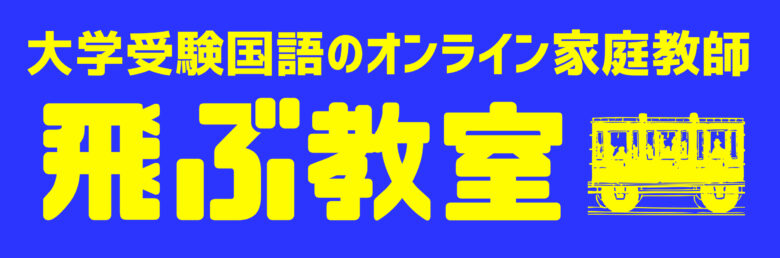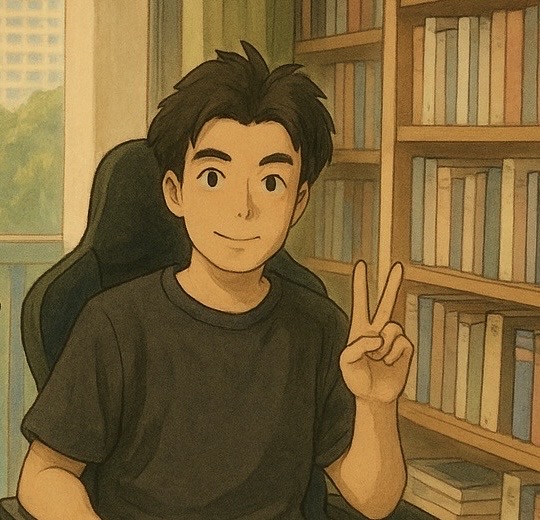授業後、夜散歩しながらブログを書いてみました。
「飛ぶ教室」の受講生には、問題集などである程度多読することは推奨しているが、現代文の解法の本を読むことは全く勧めていない。
それでも志望校には問題なく合格できるから、授業をきちんと受ければ「解法本」はいらないだろう。
現代文の勉強の最初に読む本として、予備校講師が書いた読解術みたいな本がもてはやされる。
本屋に行けばたくさん置いてあるし、買う人は多いのだろう。
手にとって読んでみると、とても明解にテクニックが書いてある。
接続詞をマークしようとか、具体例は「例えば」の後に書いてあるとか、筆者の主張は最初か最後にあるとか色々。数学のようにシンプルな公式たちが列挙されている。
確かに、そこには傾向としてはある程度正しいものもあるだろうが、受験生がそれに気を取られて、多様な例外があることを考えないようになってしまわないだろうか。
「わかりやすい」ものがウケる。これはいつの時代も真理だろう。「ユ〇ヤ人は悪」とか「人は見た目が9割」とかもその類いだ。
私だって常に「わかりやすい」指導を求められるし、なるべくそうするよう心がけている。
私なりに「わかりやすい」解法も用意している。
でも、それで本当にいいのだろうか?
「わかりやすいこと」を求める人は、裏を返せば「自分で考えなくて済む方法」を求めているだけなのではないか?
接続詞は省略されることも多いし、主張は文章の途中に出てくることもある。主張がそもそもない文章だってある。具体例が「例えば」の後にないこともある。
現代文に限らず、言語は例外の集まりなのかもしれない。
書き方に決まりはなく、自由に書けるからこそ、読み方は複雑になり、ケースバイケースに思考しないといけない。
そんなことを言っても大多数の人はこれからも「わかりやすさ」を求め続けるだろう。それはそれでいい。
難関校を目指す人はそれではいけない。「わかりやすさ」ばかり求めずに、思考力をつけないとね。
別に人気者にならなくていいので、複雑なことを複雑なまま思考できる人も育てたいと思ったり。