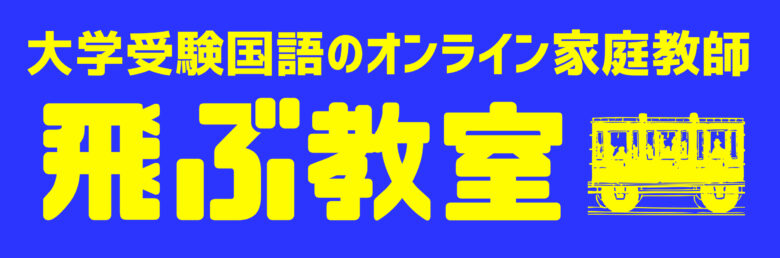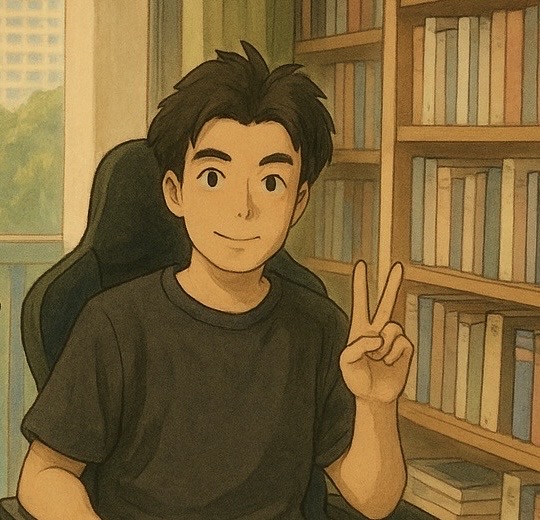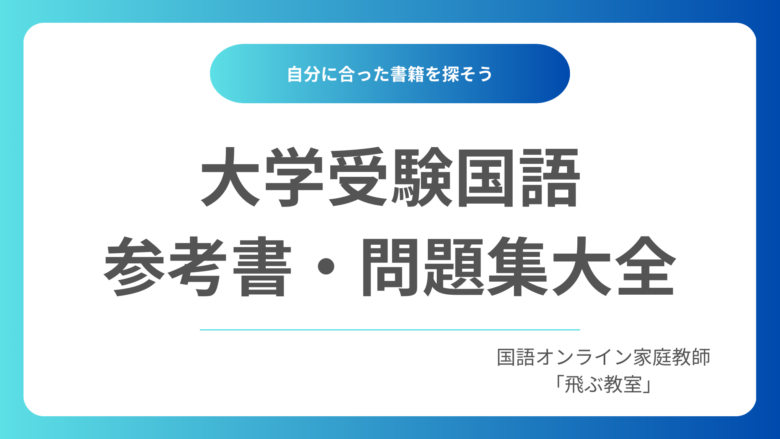こんにちは、こんばんは。「飛ぶ教室」オンライン家庭教師のけんです。
個別指導をしていると、「現代文キーワード」の単語帳に取り組むべきかよく聞かれます。もちろん、語彙力はあればあるほどいいので、時間のムダとまで言い切りませんが、何も考えずに使うと、ただ丸暗記するだけになってしまいます。では、どこに注意して読めばいいのでしょうか?
結論から言ってしまうと、難関現代文対策は「『近代』とは何か?」という問いをもって読むことが最も重要になります。よく勉強されている方の中には、「そんなの知ってるわ」と思う方もいるかもしれませんが、では、「近代に、具体的にどういう特徴があるか」聞かれて自信をもって答えられますでしょうか?
今回はこの点について解説を試みたいと思います。「私に続け、読者よ。」(※)
現代文重要単語帳の功罪
先ほど、現代文キーワードをただ丸暗記するだけなのは問題があるというようなことを述べました。その点もう少し深く考えてみましょう。
例えば、歴史科目であれば、基本的には山川などの教科書に沿って問題が作られています。そのため、教科書に合わせた一問一答問題集が出版され、教科書に載っていない知識が出ると受験生から顰蹙をかってしまいます。英語や古文も、ある程度覚えるべき単語数は決まっていて、難しい単語には注釈がつけられますよね。
しかし、現代文については、教科書などの、これを参照すればいいという基準はありません。知っておいた方がいい単語は膨大ですし、新しい単語がどんどん生まれ、さらには著者が独自の意味合いで既存の単語を使うこともあります。
確かにそういうことを考慮した上でも、現代文の重要単語集を使うメリットは2つあります。統計的に入試を分析して、頻出の言葉が掲載されていること。そして、一般的な意味を知っておいた方が、そこからずれた用法を著者がしているときに、認識しやすくなることです。
ただ、2つ目のメリットは一見もっともそうに思えますが、実際に生徒を指導していて感じることは、「単語帳に載っている一般的な意味」を絶対的に正しいと考えてしまい、本文にもそれをそのまま当てはめてしまい、間違った理解をしている人が本当に多いです。
また、この種の単語帳は、どれだけ工夫されていても、やはりスペースの問題があり、表面的な意味しか載っていないことが多いです。受験生にとっても、英語の単語帳で丸暗記することになれているため、同じように表面的な暗記の方に、易きに流れてしまいがちなんですね。
インターネットで各単語を深く調べるだけでも、ある程度の本質的な理解が得られますが、誰もがスマートフォンを持っている時代でも、逐一検索する作業を丁寧にできる高校生には、残念ながらほとんど出会ったことがありません。
(こうした問題をもっとも手っ取り早く解決するには、やはりオンライン家庭教師『飛ぶ教室』のようなところで、背景知識から手取り足取り教えてくれる教師に師事するのがよいのですが・・・)
おそらくほとんどの受験生が使っていない、とある隠れた良書を読んで、現代文という科目自体の理解を深めてから、他の勉強をすすめても遅くはないと思います。
現代文を、あるいは「近代」を考えたい受験生の必読書
俯瞰して見直してみると、「現代文重要単語集」なるものは、他の科目の暗記参考書と同様、著者によって受験生をある範囲内に閉じ込めてしまう「枠」のようにも思えます。「ここに載っている単語をしっかり覚えたら、受験に合格できるよ」と、囁きかけてくる羊飼いのようなものですかね。
一方で、現代文という科目で入試に出てくる文章の大半は、そうした「枠」の存在に気づいてくれよ、と、受験生に警告をしてくるものなのです。「常識を疑え」と、学校の現代文の先生は大仰にいいますしね。
しかし、例えば「学校」もまた、実は「近代」の産物ですよね。当時の私同様多くの高校生は、学校に何年も通っていながら、学校がどういう経緯で今の形になったのか、全く知らない不思議ないきものではありますが……。
そして、現代文は、登山家がエベレストを目指すように、まさにその「近代」という最も大きな「枠」について理解することを最終目標にしている科目といっても過言ではありません。
そのことについて正面から向き合いながら、また「現代文」という科目自体の「枠」についても俯瞰した良書が、ちくま新書から出ている石原千秋著『教養としての大学受験国語』という20年以上前の本です。大学受験に関して、筑摩から出ている本は良書が大変多く、指導の際にいつもお世話になっています。
この本の最大の特徴は、凡百の受験問題集が、雑多な問題をまず並べてそれに解説をつけているのと逆に、著者の議論の流れに沿った形で、適宜ふさわしい入試問題を、議論を深めるために選定し、掲載している点にあります。もちろん似て非なる参考書も多々ありますが、たいていは「対比」「言い換え」「逆説」など、受験上の読解テクニックの持論の正しさを示すために問題を選んでいるだけで、こういうのを「易きに流れる」と言い、難関大受験者にはものたりません。
著者の議論は、主に「近代」に対するおおまかな理解を目標に進められ、それを構成する「自己」「大衆」「権力」のあり方が章ごとに深められていきます。また同時に、入試問題の出題者の視点から、各々の設問の作成意図までも批判的に語られていきます。
この本を順に読んでいくことで、著者の思考をインストールして、最終的には「近代」そして「現代文」という科目を俯瞰的に眺められるようになれば目標達成です。2周はした方がよいとは思いますが。
「はじめに」から心に残った箇所を引用させていただきます。
もちろん、こういう二項対立を使った思考の方法自体が実に「近代」的であることはよく承知している。……(中略)
石原千秋『教養としての大学受験国語』(ちくま新書)「はじめに」より
……「近代」を問い直す文章自体が、二項対立のレトリックを用いずには成立しないのだ。
断片的ですが、おわかりいただけるでしょうか。すなわち、「近代」を問い直す現代文の入試出題文がもっとも頻繁に用いる二項対立(「自己/他者」のように相反するように見える概念を持ち出し、比べて考えること。これを「対比」とも言う)の文章構成方法自体が、まさしく「近代」的な方法である。現代文はいわば、「外側からしか鍵を開けられない部屋に、その鍵を持ったまま閉じ込められながら、なんとか脱出を図ろうとする無謀な試み」なのかも知れないということですね……。
過去問や問題集を「近代」に注意して読む方法
これまで考えてきたことから言えること。それは、「重要単語を理解するときは『近代』との関わりを考えよう」ということです。でももちろん、並大抵のことではないですよね。単語を見て一々「近代」に思いを馳せるなんて……。
なのでまずは、過去問や問題集の文章のテーマが、「近代」とどう関係しているのか、考えることをおすすめします。できれば、そのリストを作ってみてください。
一例として、当塾の生徒と、実際に早稲田文学部の過去問を何年分か読んでみて、テーマを整理したものをご紹介します。
・2020年第1問:規律権力
・2020年第2問:近代的自我
・2019年第1問:資本主義
・2019年第2問:平等
・2018年第1問:ナチズム
・2018年第2問:民族学
詳しい解説は控えますが、このように、すべてが「近代」になって出来上がった事象、あるいは「近代」を象徴する特徴について論じた文章だということがわかります。もちろん、近代と直接関わりのないテーマの文章も出題されますが、それは変化球。まずはストレートを打てるようになりましょう。
例えば、章立てが「文化」「言語」「哲学」「社会」「随想」のような抽象的な題になっている参考書であっても、自分なりに問題のテーマを「近代」に関連付けて整理しても面白いと思います。
まとめ
すこし難解なところもあり、また、敢えて「近代」が何か、ド直球に書きはしませんでした(できませんでした)が、お読みいただいてありがとうございます。
ご興味を持たれた方は、是非オンライン家庭教師「飛ぶ教室」へご応募ください。
無料体験実施中です。お待ちしております。
ではでは。
※ウクライナの作家ブルガーコフ著『巨匠とマルガリータ』より引用。